女性人権機構は女性が直面する人権問題に取り組み、
問題解決を目指す団体です。
【2025.3.6】(シンポジウム)「ハラスメントのない議会へ ~女性の政治参加を加速するために」
2025 年 3 月 26 日(水)に開催しましたシンポジウムの要旨を報告いたします。ご参加いただきました皆さまにお礼と、このシンポジウムの内容が今後の活動の参考になれば幸いです。
「議員や議会が関係するハラスメントの法規制」
モデレーター 内藤 忍氏 独立行政法人労働政策研究・研修機構 副主任研究員
【要旨】
最初に、内藤忍氏より議員や議会が関係するハラスメントの法規制について解説をいただきました。議会関係でのハラスメントとは議員同士のハラスメントと議員から自治体職員に対してのハラスメントが課題となっており、後者については条例を定めている自治体は増えてきていると、報告がありました。
2021年に改正された候補者男女均等法において、セクハラと妊娠出産に関するハラスメントの防止及び国と公共団体の措置義務が強化されたことを説明しました。さらに、多くの議員が議員同士から、または有権者などからハラスメントを受けると答えていた調査結果を報告しています。議員や議会に関するあらゆるハラスメント防止にはハラスメント行為そのものを規制する法整備や公正で中立的な判断を下せる機関を設置することでハラスメントをなくしていくことにつながると強調されました。

「候補者・議員に対するハラスメントの実態と対応について」
シンポジスト 濵田 真里氏 Stand by Women 代表、女性議員のハラスメント相談センター共同代表
【要旨】
「Stand by Women」は 2021 年に立ち上がった団体で活動内容の紹介から説明をいただきました。政治の場でのジェンダーギャップ解消のため、女性による女性議員のサポートを主旨としており、そこから見える女性が受けているハラスメントと相談の現状を説明いただきました。2021 年 5 月に改正候補者男女均等法が施行されているが、選挙の現場は男性中心であり、女性の選挙ボランティアが依然として少ないことは、ハラスメントが減らない一因では、と分析されています。女性議員にとっての相談窓口が少ないため、「女性議員のハラスメント相談センター」を受け皿のひとつとして立ち上げたが、本来は自治体で行うべき、というご指摘もありました。ハラスメントは候補者や議員本人だけでなく、その家族もハラスメントを受けるケースがあり、こうしたハラスメントを起こさせない仕組みつくりや第三者介入も必要であると提言されています。
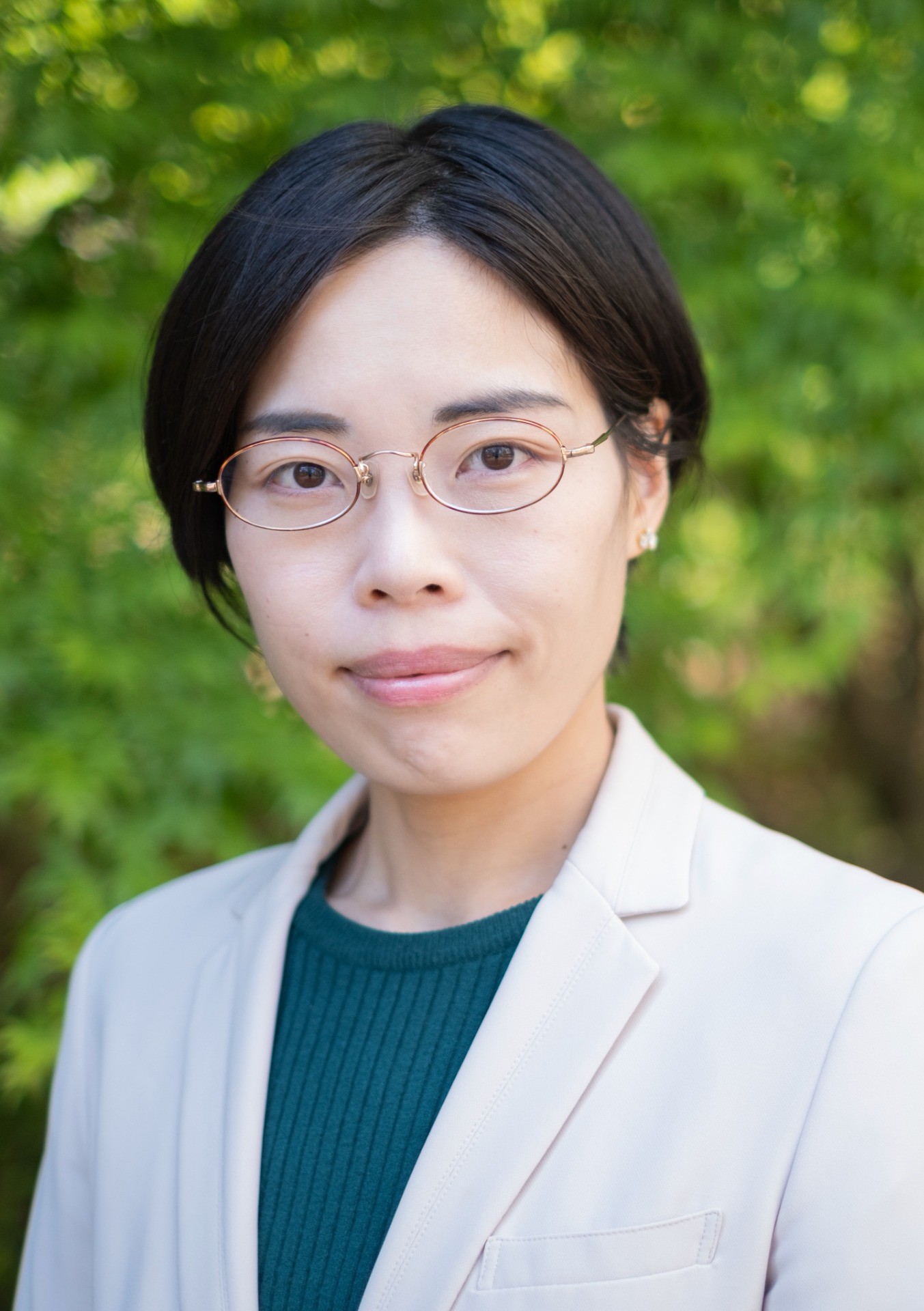
「ハラスメントのない議会に ~地方議会の現場から~」
シンポジスト 金繁 典子氏 愛南長議会議員
【要旨】
愛媛県愛南町議会議員の金繁典子氏からは女性議員へのアンケートの結果報告から見る議会で起きるハラスメントの現況と提言をいただきました。愛媛県はジェンダーギャップ指数が全国平均を下回っている現状を説明されました。ジェンダーバランスが確保されずに意思決定されている社会は問題となっており、 2024 年9月に「えひめ女性議員ネットワーク」を設立し、女性議員同志の情報交換やネットワーク作りを主旨とした活動を行っており、女性議員に議員活動とハラスメントに関するアンケートを実施しました。「ハラスメントを受けたことがある」は多くの女性議員が答えており、実例としては「黙れ、女が!とヤジを飛ばされた」「大声で恫喝された」「会議で冷笑されたり、無視された」
「男性議員に偉そうだ、と言われた」などが報告されましたが。少ないながらも女性議員は「ジェンダー平等、福祉、教育、環境、平和、議会改革」「非正規雇用の差別的取り扱いの是正」「審議会などでの女性比率の改善」「男性の育児休業の目標設定」「給食の無償化」などの行政課題を取り上げています。議員のほとんどが 60 代以上の男性なので、古くからの家父長制が影響していると思われるため、ハラスメント防止を規定する条例の制定が必要ではあるが、運用には慎重にすべき点もあると指摘されました。
ハラスメントのない議会にするためには客観的な第三者機関を相談窓口、判定機関としてを設置することが解決につながるのでは、と提言されました。
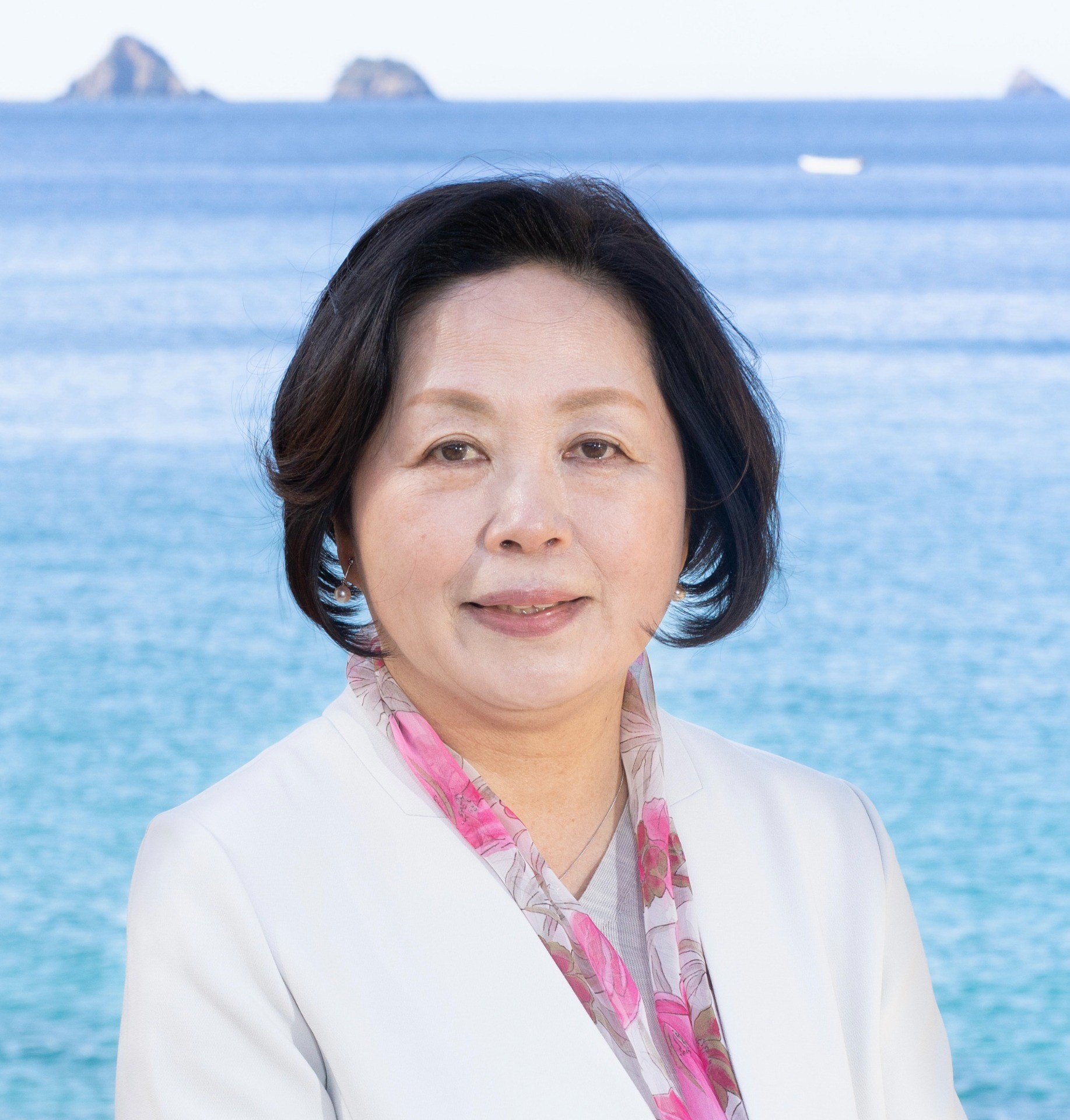
質疑応答
Q: 「あらゆるハラスメント」防止の条例を取り入れている事例は?
A: 自治体と一緒に議員、市民を守るという事例があれば、ぜひ、教えてほしい。
Q: ハラスメント規程設置のデメリットとは?
A: 判断は議長にゆだねられ属人的な判断になりがち。また、派閥争いにもなりがち。推察された内容で問責決議をされてしまう。
Q: 職員への質問がハラスメントと疑われてしまったことがあったか?
A: 少数派いじめのようなことになりがち。相談窓口、救済方法は課題。「相談」は 50%以上ができていないとの結果があり、客観的に判断できる組織が必要
Q: 相談の受け皿として(金繁さんが)提案している町村議会議長会とは?
A: 研修の紹介を受けている。相談窓口を設定してくれればと思っている。
Q: 男性優位とジェンダー平等の主張のバランスをどう取るか?
A: 男女平等を主張しつづければ良いのでは。アプローチ法を工夫、住民に理解してもらうことを意識する。日頃から女性ネットワークを活用し、大事にする。
Q: 職員からのハラスメントの対応について?
A: 公職選挙法に関わることを言われることが多いようだ。所属政党に相談や毅然とした態度で対応。
Q: ハラスメントを乗り越えて活動している例は?
A: 議員同士では難しい。会派内では分裂、報復の可能性もある。ハラスメント条例にも「報復禁止」を謳う必要もあるのでは。労働ハラスメント法制には「報復禁止」は入っている。
Q: 海外で参考になる事例は?
A: イギリス議会には公的な相談窓口が設定されている。制度設計は参考になるのでは。日本では相談体制が脆弱、一括した相談窓口や第三者機関の設置が必要。
アンケートからの声
掲載にご承認いただいた方のみ掲載しています。
- 時宜にかなったテーマで、理論、現場等の多様な角度からの報告と、登壇者相互や参加者との質疑応答という内容で理解が深まりました。
- 女性議員が受けているハラスメントについて、知ることができてとても驚いた。今、若い女性が選挙に出ようとしているので、応援している。
- 県内の某市で近く議会のハラスメント防止条例または規定を作られるとのことで、少し相談を受けていたので、ものすごく参考になりました。相談対応者の人的資源の不足やハラスメント認定までの手順やルール、認定された場合の被害者側・加害者側双方への対応とその後に配慮すべき点など、実際に運用する際には難しい事柄がいくつも予想されますが、こうした場で情報が共有されていることがとても心強いです。
- ハラスメントの問題は古くて新しいというか、日本の制度整備の遅さ、ハラサーの旧態依然としたマインドに、日本社会、学校でのジェンダー平等教育の充実さが求められると感じました。
- 行おうとしている議会でのハラスメントをなくす活動に生かせる内容でした。
- 金繁さんの発言にとてもエンパワメントされました。実際に踏み出すのを躊躇していたり迷ったりしている女性たちに、仲間がいれば大丈夫!と実際の金繁さんの議員活動が目に浮かぶようで、頼もしかったです。
- 議員の方の生の声(問題点)を拝聴できて、研究では可能でも実際はそうはならないことがよ く分かった。
- ハラスメントに多少敏感な社会になりつつあると思っているが、選挙や政治活動の場面ではいつになったらハラスメントがなくなるのか、有効な処方箋はあるだろうかと悲観的になる。
社会を変えるためにできることがあります
人権とはすべての人が生まれながらにして持っている基本的な権利です。
一人ひとりが人権の大切さを考えれば、社会を変えることができます。
会員入会やご寄付を行うことで活動を支援してください。



